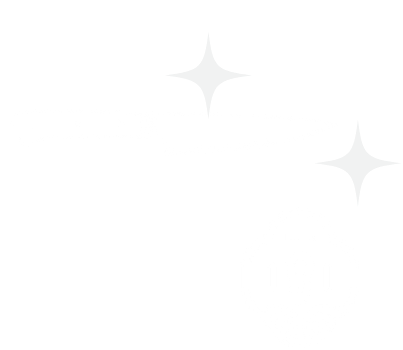うなぎ裂きの種類と選び方
だんだんと暑い日が増えてきましたね。
特に暑いのが苦手な人は夏バテには気を付けていると思いますが、その予防として思い浮かぶのが「うなぎを食べる」人が多いですね。
うなぎはビタミン類などの栄養が豊富で、夏の暑さで弱った身体に精がつくものとしては理にかなったものだそうです。
うなぎ裂きの種類って実は1種類ではないって知っていますか?
そのうなぎを捌くにも専用の包丁があるのですが、その包丁がいろいろな種類があるのをご存じでしょうか。
もともと和包丁には同じ種類の包丁で型が分かれていることがあります。
例えば薄刃包丁などは「鎌型」と「江戸型」に分かれていたり、刺身包丁も実は「柳刃包丁」と「たこ引き」に分かれて使用されていました。
大体が西(関西)と東(関東)で包丁の種類が分かれることが多いです。
主に「江戸型」、「大阪型」、「京型」、「名古屋型」の四種類があります
その中でもうなぎ裂きはさらに特殊で、使用される地域ごとに型が分かれていて、その形状も大きく異なる形をしています。
代表的な種類として「江戸型」、「大阪型」、「京型」、「名古屋型」の4種類があります。
当社では販売していませんが、「九州型」などの他の地域にもうなぎ専用の包丁の型が存在します。
なぜこんなにも型が違うのかは定かではありませんが、うなぎが昔から各地域ごとに様々な調理法で作られてきたからなのでしょう。

江戸型うなぎ裂き
うなぎ裂きの包丁で一番思い浮かぶのこの型ではないでしょうか。
その名の通り江戸(関東)方面で使用されていたうなぎ裂きになります。
関東ではうなぎを背開きにして捌いた後、頭を落としてからセイロでうなぎを蒸します。
そのため江戸型にはうなぎの背をひらく刃と、頭を落とす刃の二か所が有るのが特徴です。
なぜ背開きなのかと言いますと、江戸では腹から捌くと侍の切腹を連想させるために背開きになったと言われています。

大阪型うなぎ裂き
こちらは大阪で使用されてきたうなぎ裂きになります。
うなぎ裂きの種類の中では一番シンプルな型をしており、あくまでもうなぎを裂くためだけに使用します。
関東とは逆に腹開きでうなぎを捌き、背骨と内臓を取り出して蒸さずにそのまま焼いていきます。
調理法はシンプルですが、腹開きは背開きよりも捌くのが難しく熟練の技が必要とされるので、捌きやすいこの型になったのだと思います。
なぜ大阪型は腹開きなのかと言いますと、大阪は商人の街のため「腹を割って話す」と言われていることから腹開きになったとされています。

京型うなぎ裂き
数あるうなぎ裂きの中でも一番独特な形をしているのがこの京型のうなぎ裂きになります。
こちらは京都で使用されている包丁です。
一番最初に目につくのが極端に厚くなった刃の峰側です。
これはうなぎを捌くとき、目打ちを打つ際に使いやすいようにこの形に作られています。

名古屋型うなぎ裂き
こちら名古屋を中心に中部地方で使用されてきたうなぎ裂きになります。
うなぎ裂きの種類の中では小型で幅も細いので、取りまわりが利き使いやすい包丁です。
小型ではありますが、刃は鈍角な刃付けがされているので、荒い使い方をしても刃こぼれが出にくいです。

以上のようにうなぎ裂きは地域ごとに様々な形があり、その形状にあった使われ方がされてきました。
正直どの包丁が使いやすいのかは、プロの料理人にしか分からない世界だと思いますので、もし趣味でうなぎ裂きを使いたい方などは鰻屋に聞かれるのが一番いいとは思います。
地域によってこれだけ包丁の形が変わるのは、日本の和包丁の面白いところですね。