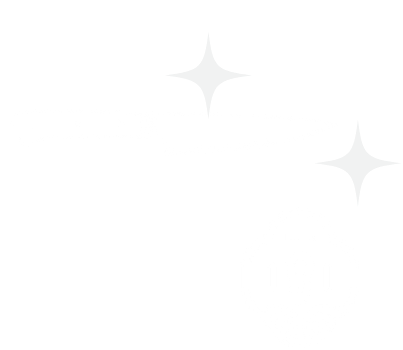家庭用包丁(三徳包丁)の研ぎ方
家庭用包丁は基本的には刃の構造が牛刀と同じですので、「牛刀の研ぎ方」と同じように研いでいただくのが理想です。
ですが、この研ぎ方はプロの料理人向けの難易度の高い研ぎ方ですので、少し難易度を落とした初心者向けの研ぎ方をご説明させていただきます。
この研ぎ方を覚えつつ、どんどんと上達してきたら「牛刀の研ぎ方」をチャレンジしていただく事をお勧めします。
研ぎの基本を覚える
包丁を研いだことがないと言う方も沢山いると思います。
その場合はまず研ぎ方を知る前に研ぎの基本を覚えていきましょう。
砥石の選び方
「中砥石」を選んでください。砥石に種類は荒さ(番手)によって「荒砥石」「中砥石」「仕上げ砥石」の三種類に分類されます。
もちろんこの三種類には研ぎの役割があるのですべて揃えてもらう事が理想ですが、初めての方でしたらまず「中砥石」が一つあれば大丈夫です。また両側荒さの違う両面砥石も便利です。
研ぎの姿勢
包丁の持ち方は表(右面)を研ぐ時、右手人差し指から中指まで3本の指で柄を握り、人差し指で峰を親指を刃元にそえるようにしてください。
包丁の動かし方は砥石に対して45度に当てて真っすぐ押すように動かしてください。逆に引くときはあまり力を入れないでください。

研ぎの角度
基本的には両刃の包丁を研ぐのに決まった角度が存在しません。
なので研ぎ慣れていない内は研ぎの角度を約10度~15度くらいにして研ぐのがいいと思います。
よく言われているのが硬貨が2枚重ねた時の角度くらいが理想です。

どこまで研げばいいか
初心者でも分かりやすい確認の仕方がかえりを確認する方法があります。研ぎ進めて行くと研いでいる反対面の刃先にざらつきが出てきます。
これを「かえり」といい刃先まで研ぎきった金属が反対側にめくれてきます。これが出ている箇所は研げています。

包丁の状態を確認する。
まず研ぎを始める前に包丁全体を目で確認してください。
包丁研ぎはただ切れ味を戻せばいいという訳ではなく、包丁の正しい形を維持するためにも研ぐものです。それを意識しないまま研ぎ進めていくと包丁の形が崩れて包丁の寿命が短くなります。そのために必ず刃の状態を確認する癖をつけてください。

中砥石で右面の刃先を研ぐ
45度に刃を立てて研ぎます。
使用する砥石は中砥石です。
切れなくなった状態とは刃先が丸まってツルツルとした状態です。まずそこを直すために刃を45度に立てて刃先のみ(小刃研ぎ)を研ぎます。


刃先に二段刃が出来ます。
刃を立てて研ぐと刃先に小さな二段刃が出来ます。
目で確認しますと光の加減で刃先に白い線が見えますが、それが刃先が二段になっておりこれを「小刃」と呼んでいます。
この小刃(二段刃)が一番刃先の先端になり、ここを基準に研ぎ進めて行きます。

刃の角度を寝かせて研ぐ
小刃(二段刃)が消えるまで研ぐ。
この小刃(二段刃)の状態ですと、刃先が厚いのでこのままでは鋭い切れ味にはなりません。
そのため先程よりも研ぎの角度を寝かせて刃を研ぎます。
使用する砥石は中砥石です。

研ぎの角度は約10度~15度が目安です。
最初は45度の角度で刃先だけ研ぎましたが、今回は角度を10度~15度を目安にして研いでください。分かりやすく言いますと、「硬貨が二枚重ねた時」の角度になります。この角度で研ぐ場合は、最初の刃を立てた研ぎ方よりも刃を削る量が多くなるため、研ぎ時間も多くなります。
大変な作業になりますが、根気よく研いでください。

手首は固定してください。
その角度が決まったら、前後に動かして研ぎ進めて行くのですが、この時に注意するのが「研ぎの角度を変えない」事です。
どういうことかと言いますと、研ぎは手首と肘を使って研ぐのですが、どちらも関節なので研いでいる最中にブレてしまいます。そうなると最初に決めた角度が崩れてしまいます。特に研ぎの角度を決めるのは手首になりますので、研ぐ時は必ず手首は固定して研ぎ進めてください。
※なかなか刃が削れないからと言って刃の角度を立てたりしないでください。手首を固定して、最初の10度~15度の角度を維持してください。
研ぎ幅が広がります。
切っ先から刃元まで均等に研ぎ進めて行ってください。
そして研ぎながら、研いだ箇所を目で確認してください。刃を寝かせて研いだため、最初に研いだ小刃よりも研いだ箇所が広がっていると思います。もし研ぎ幅があまり変わらないようでしたら、角度が立っているのでもっと刃を寝かせる必要があります。

小刃が消えているか確認します。
切っ先から刃元まできちんと研げましたら、刃先を見て最初の小刃が消えているか確認してください。消えているのを確認しましたら反対側の刃先にかえりが出ているかも確認してください。
切っ先から刃元まで小刃が消えて、かえりが出ているのでしたら右面はきちんと研げています。

左面(裏)も同じように研ぐ
左面を研ぐ時の角度も出来る限り右面と同じ角度にして研いでください。
そうすることで両側の角度が揃った両刃になります。

右面と同じ角度で研ぐ
左面を研ぐ時の角度も出来る限り右面と同じ角度にして研いでください。
そうすることで両側の角度が揃った両刃になります。

かえりが出るまで研ぐ。
左面も右面と同じように切っ先から刃元まで均等に研いでいきます。反対側(右面)の刃先にかえりが出ているか確認してください。
切っ先から刃元までかえりが出ていたら左面もきちんと研げています。
小刃引きをする
この時点で切れる刃は付いておりますが、この状態は逆に刃先が薄すぎて刃こぼれがしやすくなります。そのため最後にも小刃引きをして刃先に強度を持たせることをお勧めします。
小刃引きのやり方は、最初と同じで刃を45度に立てて刃先だけ研ぐだけです。ただ最初と同じ力で研ぐと刃先が厚くなり過ぎてしまいますので、軽い力で砥石の上を滑らすように動かしてください。回数は2~3回くらいで止めてください。反対側にかえりが出ているか確認をしてください。
かえりが出ているのが確認出来ましたら反対に持ち替えて、軽い力で左面も研いでください。


かえりを取る
今の状態でも切れる刃は付いていますが、かえりが残っていると切った時にざらつきがありますのでかえりを取ります。
家庭用で簡単に取れる方法が二つあります。
①新聞紙でかえりを取る
②要らない布生地でかえりを取る
刃先を擦り合わせる
新聞紙や布生地に刃先を擦るように動かします。
両面の刃先を共に五回ずつくらい擦りますとかえりが取れます。

新聞紙で試し切りをする
研いだ包丁がきちんと刃が付いているか新聞紙で試し切りをして切れ味をチェックしてください。新聞紙がスムーズに切れましたらきちんと刃が付いています。
もし新聞紙が引っかかる箇所があったらその箇所の刃はまで研ぎきれていません。